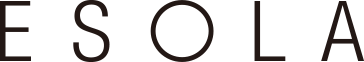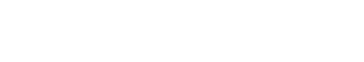2025.04.30
中古住宅の解体に掛かる費用は?解体するまでの流れと必要な手続きも解説
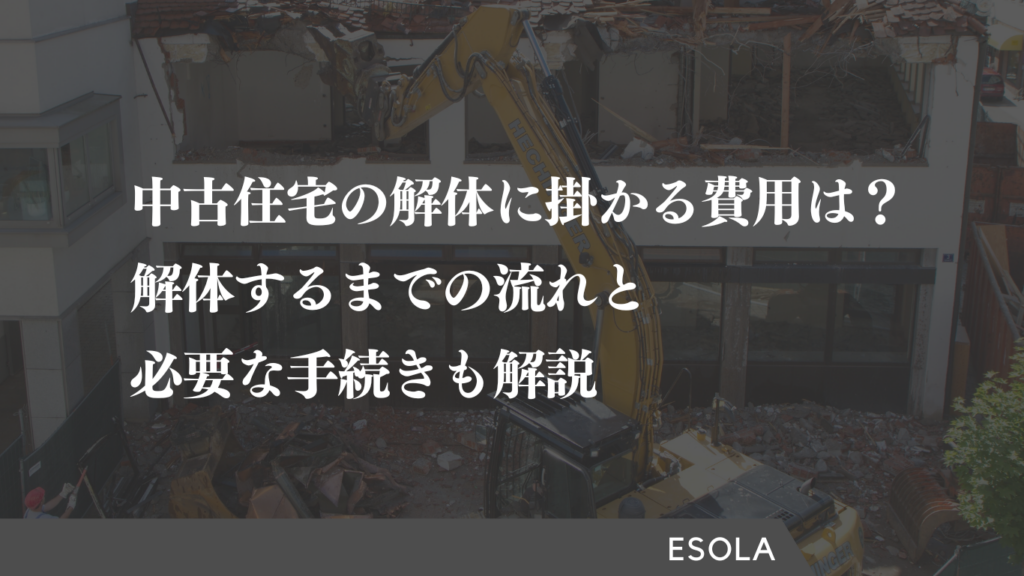
土地を探していると、良い立地だけど中古住宅が建っており、新たに住宅を建てる際に解体が必要な場合があります。中古住宅の解体は、費用が掛かるだけでなく、さまざまな手続きが必要になるので、面倒に感じる方も少なくないはずです。
しかし、補助金を使用したり、必要な手続きを理解しておけば、中古住宅が建っている好条件の土地を取得し、新築住宅を建てられます。
本記事では、中古住宅の解体費用や解体までの流れを中心に解説します。記事の後半では、中古住宅を解体する際の注意点や補助金についても解説しているので、これから中古住宅の解体をしようと考えている方は最後までご覧ください。
新築計画の進め方でお困りではありませんか?
- 選択肢が多すぎて、どの設備が本当に必要かわからない
- このまま進めて良いのか不安が残っている
- 持っている土地の地盤調査を相談したい
エソラでは、こうした「新築に関するわからない」を解決するための個別相談会を実施しています。経験豊富なスタッフが、あなたの理想とニーズに合わせた最適なアドバイスを行います。
どんなささいなお悩みでも構いません。コンタクトページの自由入力欄より、ご相談ください。
1.中古住宅を解体する際の費用相場は?
中古住宅を解体する際には、構造のよって費用相場は大きく変わります。また、以下の建物本体の解体費用に加えて、狭小地や住宅密集地、アスベストの有無、廃材の処理費用、外構の撤去などの費用が加算されます。
基本的に中古住宅の構造は以下の3つがあります。
- 木造
- 鉄骨
- RC構造
それぞれの中古住宅の構造別に、費用相場を解説します。
木造
解体する中古住宅が木造の場合には、1坪あたり4〜6万円が相場の目安です。木造のため、他の構造に比べると費用は安い傾向にあります。大体30坪程度の住宅であれば100万円〜200万円程度の費用が掛かるでしょう。
鉄骨
解体する中古住宅の構造が鉄骨の場合には、1坪あたり5〜8万円が相場の目安です。木造住宅よりは高いですが、RC構造の住宅よりも安い傾向にあります。30坪あたりの住宅であれば、200万円〜300万円の費用が発生します。
RC構造
解体する中古住宅の構造が鉄筋コンクリートでできているRC構造の場合には、1坪あたり8〜12万円が相場の目安です。解体費用としては最も高い構造となっており、30坪あたり250万円〜500万円程度の必要が発生します。
解体する中古住宅の構造によって費用は大きく変わるため、必ず中古住宅を購入する前にどのような構造になっているかを確認しておくとよいでしょう。
2.中古住宅を解体するまでの流れ
中古住宅を解体する際には、大きく分けて以下の5つのステップの流れがあります。
- 解体業者の選定
- 許可や届出の手続き
- 解体
- 廃材の処理
- 解体後の手続き
1.解体業者の選定
中古住宅を解体する際には、まず解体業者の選定から始まります。解体業者を選ぶ際には、複数の業者に見積もりを依頼して、相見積もりを出してから費用の相場を理解した上で選ぶと業者選びに失敗しにくくなります。
また、解体業者を選ぶ際には、口コミや実績を必ず確認して、信頼できる業者かどうかを検討するようにしておきましょう。
2.許可や届出の手続き
中古住宅を解体する前には、解体に必要な許可や届出などの手続きが必要です。解体前に必要な許可や手続きには、以下のようなものがあります。
- 解体工事の届出
- 道路使用許可の届出
- ライフラインの停止
- アスベスト調査と届出
中古住宅を解体する際には、床面積が80㎡以上の場合、自治体に「解体工事届出」の提出が必要であり、工事する1週間前までに提出しなければなりません。
解体する際に、隣接する道路を使用する際には警察署に「道路使用許可申請」の提出が必要です。
また、ライフラインも事前に停止手続きをしておかなければなりません。停止する期間については、解体業者と相談した上で決めてから停止手続きをするようにしましょう。
3.解体
解体前の許可や届出が完了したら、解体作業に入ります。解体中は、特に必要な手続き等はありませんが、定期的に解体作業を見学しに行き、適切に解体が行われているかを確認しておくとトラブルを回避できます。
4.廃材の処理
中古住宅の解体後には、廃材の処理が必要です。基本的には解体業者が廃材まで処理してくれるため、任せておいて問題ありませんが、見積もりの時点で、廃材の処理まで含まれているかを確認しておきましょう。
5.解体後の手続き
中古住宅の解体が終了し、廃材まで処理されたら、以下の2つの手続きや確認が必要です。
- 建物滅失登記の申請
- 固定資産税の確認
解体が終了したら、管轄の法務局に「建物滅失登記」を申請して、登記簿から中古住宅の情報を削除しなければなりません。「建物滅失登記」は解体終了後1ヶ月以内に申請する必要があります。
また、土地が更地になると固定資産税が変わるため、自治体の税務局に確認の手続きが必要です。解体後に住宅を建てる場合にも固定資産税がどうなるかを確認しておくと安心です。
3.中古住宅を解体する際の注意点
中古住宅を解体する際には、理解しておいた方がよい注意点があります。注意点を理解しておかないと、無駄な費用が発生したり、手続きを忘れてしまったりする可能性があります。中古住宅を解体する際の注意点は、主に以下の4つがあります。
- 事前の手続き
- 業者選び
- 廃材の処理
- 解体後の手続き
事前の手続き
中古住宅を解体する前のさまざまな手続きをしなければ、違法工事になってしまうので漏れがないように注意が必要です。事前の手続きには以下のようなものがあります。
- 解体工事の届出
- 道路使用許可の届出
- ライフラインの停止
- アスベスト調査と届出
上記の届出以外にも、近隣住宅に挨拶や説明をしておくと、解体後にトラブルが発生しにくくなるため、工事が始まる前までに挨拶を終わらせておくようにしましょう。
業者選び
中古住宅を解体する際には、業者選びが重要です。適当に業者選びをしてしまうと、費用で騙されたり、工事の内容が悪かったりする可能性があるためです。そのため、業者選びをする際には、3社以上で相見積もりを取ることと、実績や口コミを確認しておくようにすると、業者選びで失敗しにくくなります。
廃材の処理
中古住宅を解体する際には、廃材が出るため、確実に廃材の処理がされているかの確認が必要です。基本的には、解体業者が廃材処理までしてくれますが、廃材が残っていないかなどの確認をしておきましょう。
解体後の手続き
中古住宅を解体した後にも手続きが必要です。土地から建物が無くなるため、法務局に「建物滅失登記」をして、中古住宅の情報を削除しなければなりません。また、解体後の土地に建物を建てようと考えているのであれば、整地作業を行い、必要に応じて測量や地盤調査が必要になります。
地盤調査に関しては、以下の記事で詳しく解説しているので参考にされてください。
4.中古住宅の解体には補助金が出る可能性も
中古住宅を解体する際には、自治体によっては補助金が出る可能性があるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
例えば、群馬県の前橋市では上限25万円の補助金が出る「空き家対策補助金」があります。
補助金を受けるためには、さまざまな条件が設けられている場合がほとんどであり、自治体により条件は異なるため、中古住宅がある自治体に補助金の制度がないかを問い合わせておくと良いでしょう。
5.まとめ
今回は、中古住宅を解体する際の費用相場や解体の流れを中心に解説しました。
中古住宅を解体する際の費用相場は、中古住宅の構造によって大きく変わります。そのため、解体する際にはまず構造がどうなっているかを確認しておきましょう。
中古住宅を解体する流れは、必要な手続きを忘れないように注意しながら、業者選びも複数社で相見積もりを取って、依頼するようにすると安心です。
また、中古住宅を解体する際には、住んでいる自治体によって補助金が出る可能性があるため、業者に依頼する前に補助金が受けられるかを、役所に問い合わせたり、ホームページで確認しておくと良いです。
中古住宅が建っている土地をこれから購入して、解体しようと考えている方は、必要な手続きを理解し、適切に業者選びをすることで、安心して解体できるので、事前に流れを十分に理解しておきましょう。
新築計画の進め方でお困りではありませんか?
- 選択肢が多すぎて、どの設備が本当に必要かわからない
- このまま進めて良いのか不安が残っている
- 持っている土地の地盤調査を相談したい
エソラでは、こうした「新築に関するわからない」を解決するための個別相談会を実施しています。経験豊富なスタッフが、あなたの理想とニーズに合わせた最適なアドバイスを行います。
どんなささいなお悩みでも構いません。コンタクトページの自由入力欄より、ご相談ください。