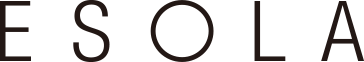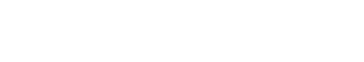2025.10.25
建築資材の高騰は2025年以降も続く?高騰している7つの原因や今後の見通しを解説
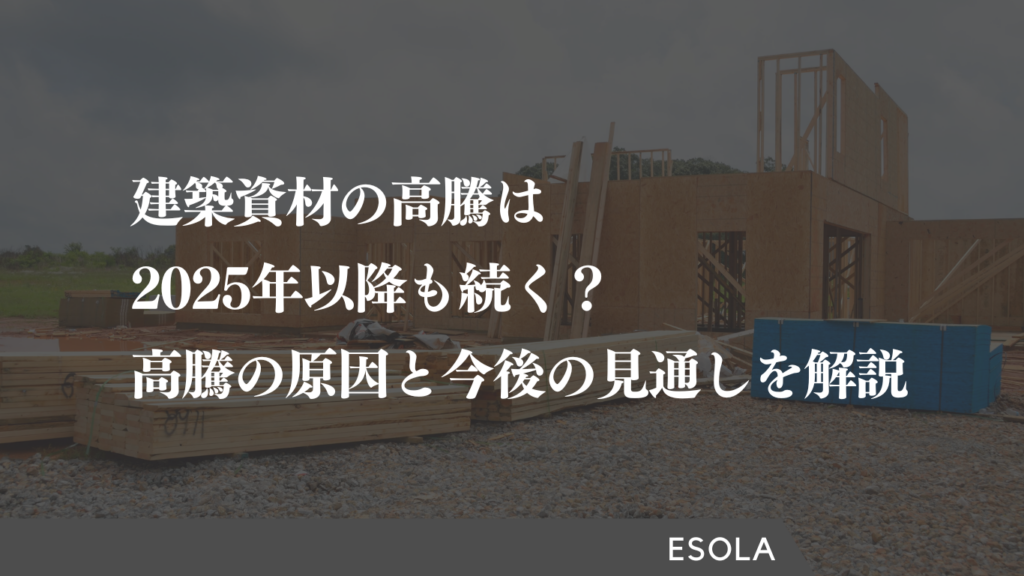
「家を建てたいけど、費用がかなり高い…」
「なぜ建築資材が高くなっているの?」
マイホームを持ちたい方にとって、建築費用はもっとも気になるポイントですよね。
近年、住宅の建築費用は上昇傾向にあり、その主な要因の一つが建築資材の価格高騰です。この高騰は一時的なものではなく、現段階で値下がりは期待できないと推察されています。
そのため、これから住宅を購入する人は、今後の高騰リスクや市場の状況を考慮したうえで適切な行動をとることが重要です。
本記事では、建築資材の価格上昇の背景や今後の見通し、これから住宅を購入する人が実施するべき対策について解説します。
20年以上の実績と500棟以上の信頼!
関西で土地から新築戸建てを考えるならエソラ
阪神間・北摂エリアで土地を探しているけど、「どこに住むべきか迷っている…」「信頼できる業者をどう選べばいい?」といったお悩みはありませんか?そんな方には、注文住宅20年以上のエソラにお任せください。
エソラブランドを展開するアプローズデザインは、これまでに約500棟を超える注文住宅の設計・建設を手がける信頼のハウスメーカーです。
これから土地を探される方や、新築を検討される方へ、エソラのブランド資料や見学会、土地探しリクエストを無料で提供しています!お気軽にお問い合わせください。
1.建築資材高騰の7つの主な要因
2021年のウッドショックを皮切りに、コロナウイルスによる物流の停滞や戦争による原料不足など、さまざまな要因が重なり、建築資材の価格が上昇しています。
ここでは、特に大きな影響を与えている7つの理由を紹介します。
ウッドショックによる木材不足
ウッドショックとは、2021年頃から世界的に発生した木材価格の急激な高騰と供給不足の現象です。
新型コロナウイルスの影響で、欧米を中心に在宅勤務が普及し、住宅需要が世界的に増加しました。その結果、日本への木材の供給が追い付かなくなり、価格が急騰しました。
現在はピーク時ほどではありませんが、まだまだ以前のような水準には戻っておらず、高止まりが続いている状態です。
日本国内でも住宅建設に必要な木材を準備することは可能ですが、国産材のみで賄うことは現状難しくなっています。輸入によって準備しなければいけないため、どうしてもコストが高くなり、高騰につながってしまいます。
アイアンショックによる鉄材価格の上昇
アイアンショックとは、木材と並んで住宅の基礎や構造に不可欠な鉄鋼資源の価格が高くなっている現象です。新型コロナウイルスの影響により世界的に住宅需要が拡大したことで、鉄鋼の需要を押し上げ、価格高騰の一因となっています。
また、新型コロナウイルスの影響が収束した後も、世界的な経済活動の再開や各国のインフラ投資の増加などにより、鉄鋼資源の需要が拡大しました。その結果、日本への供給が追い付かず、価格が高騰しています。
日本は鉄鋼資源を輸入で賄っているため、世界的な需要増加や資源国の供給不足によって鉄鋼資源の価格が上がると、ダイレクトにコスト増加につながります。
現在も鉄鋼資源の価格は高い水準で推移しており、住宅の基礎の鉄筋や、大規模建築に用いられる鉄鋼資源のコストを押し上げ続けています。
戦争による物流の不安定化
ロシアによるウクライナ侵攻は、エネルギー資源だけでなく、世界的な物流と原材料の供給に悪影響を与え続けています。
ロシアは木材、アルミニウム、銅といった建築に関わる資源の主要な輸出国です。経済制裁や情勢不安によりこれらの供給が途絶したり、輸入価格が高騰したりしています。
また、ウクライナで紛争がおこなわれることで輸送ルートが制約され、資材を別の経路で運ぶ必要が出ています。その結果、輸送時間が長くなったり、余分に燃料費がかかってしまったりなど、間接的に鉄鋼資源のコストを増加させる原因となっています。
円安による輸入コストの増加
円安とは、外国の通貨(ドルやユーロなど)に対して円の価値が下がっている状態を指します。
日本では、木材や鉄鋼などの建築資材の多くを輸入に頼っています。輸入比率が高い資材は円安の影響を受けやすく、仕入れ値が大幅に上昇します。そのため、ダイレクトに建築費用に影響を与えるのです。
光熱費の高騰による製造コストの上昇
建築費用が上昇している背景には、資材の単価だけでなく、電気代やガソリン代などのコストが増えたことも原因の1つです。
世界的なエネルギー供給の不安定化や、円安が重なることで、燃料や電力の価格は高騰しつづけています。建物の建築には資材の製造やトラックの運搬など、多くの場面でエネルギーが必要です。
そのため電気代やガソリン代などが高くなることで、資材の製造や輸送コストも自然と上昇してしまうのです。
コンテナ不足による運輸費の高騰
新型コロナウイルスの影響により、多くの方がステイホームをおこないました。そのため世界的に外出は控えられましたが、ショッピングはネット通販でおこなうようになり、物流の需要が急激に増加しました。
物流に必要不可欠なコンテナや船のスペースが不足するほど需要は増加しましたが、それらに対応するためにはどんどんコンテナを輸送させなければいけません。しかしそのためには輸送コストがどうしても発生します。
その影響で、物流業者は運送費を上げざるを得ず、その結果、建築資材の価格にも転嫁される形となっています。
世界情勢の不安定化による半導体の不足
住宅設備機器(給湯器、IHクッキングヒーター、エアコン、換気システムなど)の多くには、制御のための半導体が組み込まれています。
しかし近年は、世界的な半導体の需要増加(5G、AI、電気自動車など)や、生産地域の情勢悪化などにより、供給が不安定化しています。
建築資材の価格上昇が、そのまま住宅設備機器の値上がりにつながっています。
2.建築資材の高騰はいつまで続くのか?
これまで見てきたように、建築資材の価格上昇にはさまざまな要因が影響しています。現時点では建築費が大幅に下がる見通しは薄く、しばらくは高止まりの状態が続く可能性が高いと考えられます。
2025年10月以降も資材価格の上昇が予想される
資材価格はピーク時の急激な高騰からはやや落ち着いていますが、短期間で大幅に下がることは見込みにくい状況です。むしろ、2025年10月以降も上昇傾向が続く可能性があります。
- 輸入国からの供給不足による木材・鉄材の不足
- 世界情勢の不安定化によるエネルギーコストの増加
- 円安の長期化
- 光熱費の高止まり
- 人材不足による人件費(労務費)の上昇
また、これらの原因は複合的に作用します。仮に一部資材の価格が下がったとしても、建築にかかる総費用としては依然として高い水準が続くと考えられます。
住宅ローンの融資金利も上昇傾向に
建築資材の高騰だけでなく、住宅ローン金利も上昇傾向にあります。
2024年3月のマイナス金利政策解除以降、日銀は金融政策の正常化を進めており、短期・長期金利ともに引き上げを進めています。長期金利に連動する固定金利(フラット35など)はすでに上昇しており、今後も高くなる見通しです。
また、金利の上昇は、物価上昇による経済への影響も関係しています。
近年、国内の賃金と物価は上昇傾向にあります。賃金と物価の循環を良くすることは経済の活性化につながると考えられ、好循環を目的に政策金利の引き上げがおこなわれるかもしれません。
3.これから住宅を購入する人が実施するべき対策
これから住宅を購入する人は、今後の高騰リスクや市場の状況を考慮したうえで適切な行動をとることが重要です。ここからは、これから住宅を購入する人が実施するべき以下の対策を解説します。
- 費用上昇のリスクを意識して計画を立てる
- 中古物件や狭小住宅を検討する
- 費用に関して密に相談できるハウスメーカーに依頼する
費用上昇のリスクを意識して計画を立てる
住宅の新築を検討している方は、資材価格の上昇リスクを踏まえて、計画的に行動することが大切です。検討期間が長引くと、現状の高騰が続く中で建築費用が急激に増える可能性があるため、早めの判断が求められます。
「数年待てば安くなるかも」という期待は持たず、現状の水準が続くことを前提に、迅速かつ計画的に動いていきましょう。
ただし、費用の高騰リスクに焦って、無理なローンを組むことは禁物です。市場や金融動向は急激に変化する場合もあります。無理に借り過ぎず、金利上昇リスク・返済計画を現実的に試算したうえで、将来の返済計画を慎重に立てましょう。
中古物件や狭小住宅を検討する
費用をできるだけ抑えたいなら、中古物件や狭小住宅を検討するのもおすすめです。
中古住宅は、新築に比べて資材価格の高騰による影響を受けにくいことが多いです。築年数が経過した物件でも構造体の状態が良ければ、リノベーションによって新築に近い快適性を比較的安価に実現できます。
また、狭小住宅であれば、一般的な住宅より土地や居住スペースが狭いですが、土地の購入価格や建築にあたってのコストを抑えられます。建材の使用量を減らし、工期を短縮できる設計は、建築費の直接的な削減につながります。
費用に関して密に相談できるハウスメーカーに依頼する
ハウスメーカーを選定する際は複数業者から見積もりを取って、費用に関して相談できる業者に依頼しましょう。
複数の見積もりをとることで、料金や含まれているサービス内容が比較できます。また、料金の内訳の説明や対応の仕方、知識・経験の豊富さなど、業者の雰囲気を確認することにもつながります。
雰囲気を確認するなかで、資金計画や費用を抑える方法などの相談に親身になってくれる業者を選びましょう。
実績豊富なハウスメーカーだと、住宅建築コストを抑えるための施策提案や、補助金・助成金に関する提案をしてくれるケースもあります。実績は業者のホームページに掲載されていることが多いので確認してみましょう。
4.まとめ
建築資材の価格上昇は2025年以降も続く見込みで、短期間での大幅な値下がりは期待しにくいと考えられます。
これから住宅を建てようか悩んでいる人は、費用の高騰リスクを考慮して、計画的に動くことが重要です。また、資金計画や費用を抑える方法などを考えたい方は、費用に関して親身になってくれるハウスメーカーに相談しましょう。
「理想通りのお家を作りたいけど、費用が気になる…」とお考えの方は、アプローズデザインがご提供するエソラにおまかせください。